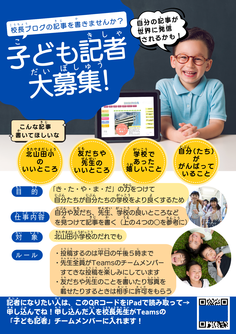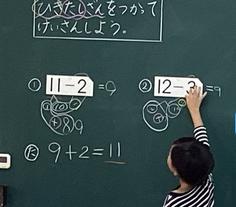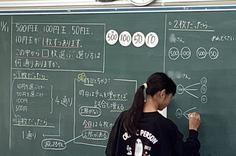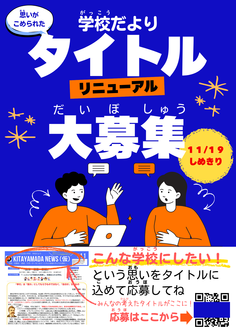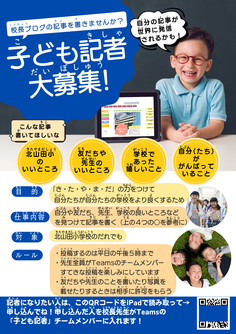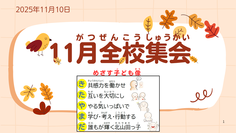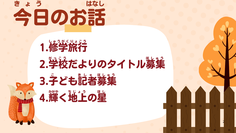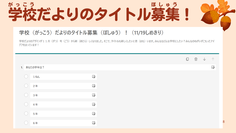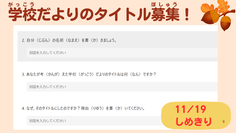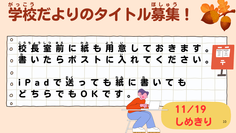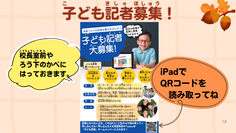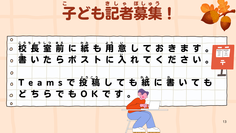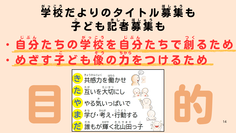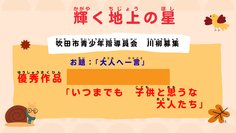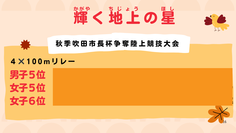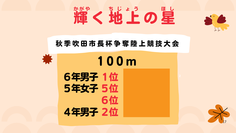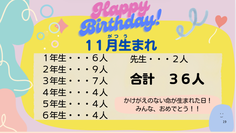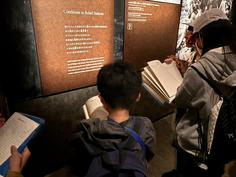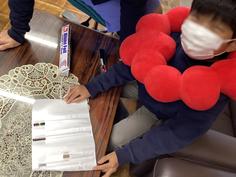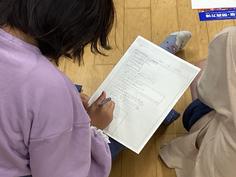3年2組は北山田フェスティバルで「フルーツしゅうかく」というお店を出します。
どんなお店か簡単に説明します。
入り口でかごを渡します。それでどの畑に行きたいか選びます。たとえば、いちご畑だったら、その畑でフルーツのへたが見えています。その一つを選んで引っこ抜きます。当たりはフルーツのヘタより下の部分がついています。
ハズレだとへたしかありません。このお店は私が考えたわけではないけど、考えてくれた人はすごく詳しいルールまで考えて提案してくれました
なので私もいいな〜と思いました。
(3年生記者Gさん)