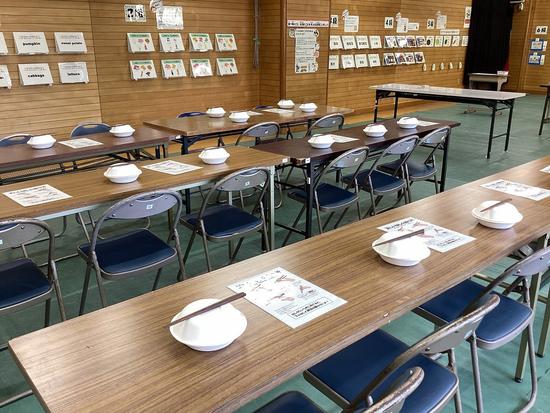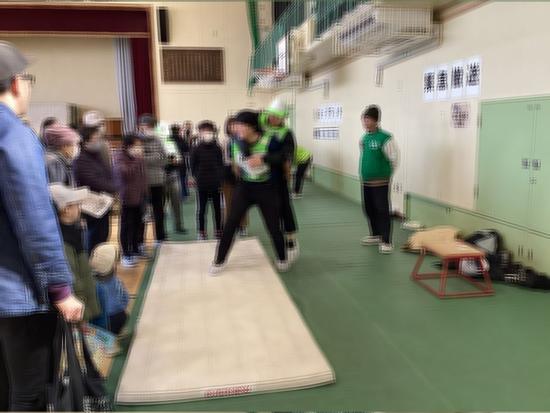明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、南山田小学校は、子どもたちは使う2つの門(正門と裏門)以外にも、車が出入りするための門が2つあります。一つはごみ庫の近くで、ごみ収集車が出入りするのに使います。もう一つは、教職員が「車両門」と呼んでいるのですが、給食室の近くで、給食の食材を運び入れたり、学校に関連する車両の出入りに使っています。緊急車両はこちらを使います。
昨年度に、教職員の研修で、救急車での搬送をシュミレーションする機会がありました。そのとき、やってみてわかったことが、車用の門が2つあるけれど、同じ色だということです。普段利用している業者さんなら間違えませんが、いざというとき、緊急車両のドライバーが、「どっちの門から入るのか?」となっては大変です。何かが起こってからではいけないので、校務員が、ペンキで車両門を青く塗りました。
これで2つの門は、「緑の門」と「青の門」になりました。知っておいてください。